播磨國美嚢郡市之瀬村文書
播磨国美嚢郡市之瀬村は今の兵庫県三木市吉川町の辺りで、村の旧家には多くの古文書が残されていた。
江戸時代は、領主から発せられた命令はすべて文書にて通達され、庶民から領主への申し立ては村役人(庄屋・組頭・百姓代など)が文書にて行っていた。
庄屋の家には、宗門人別送り状などさまざまな書類の写し、お役所への届け出・訴えの写しが保管され、現代まで伝えられている。
宗旨人別送り一札之事 -- (播磨國美嚢郡市之瀬村文書 ; 戸口2).
21121234/ 所在:貴重 / 請求記号:210.088||119
嘉永六年丑六月
上津上村の儀兵衛が播州美嚢郡市之瀬村の庄屋新右衛門宛に出した宗旨人別送り状。
利之兵衛は33歳、宗旨は禅宗の蓮花寺。市之瀬村の惣右衛門の家に養子に入ることになった。
請人は庄屋の重兵衛。
宗旨人別送り状
もともとキリスト教を禁止するため、村民がどのような宗教宗派を信仰しているか調査して「宗旨人別改帳(しゅうしにんべつあらためちょう)」を作成していた。
村を出て働く時や結婚する時、必ず「人別手形」を発行して、『こちらの「宗旨人別改帳」から名前を削除するのでそちらの「宗旨人別改帳」に書き加えてください』と依頼した。現在の住民票を移すのと同じしくみである。
夜逃げ、勘当、追放などで「人別手形」を持たずに離村すると、「無宿(むしゅく)」になってしまう。
年季奉公人請状之事. -- (播磨國美嚢郡市之瀬村文書 ; 戸口3).
21121241/ 所在:貴重 / 請求記号:210.088||119
嘉永二年正月
娘ふゆ、家が不仕合せのため、当年12月19日から寅年12月13日まで丸五年、給料銀180目前渡し、御法度や村の決まりを守り、家風の仕着せ(与えられた衣服)に文句を言わず、病気や逃亡の際は代わりの人を送ると書いている。
宗旨のことは書いていないがたいていは書く。
差出人 親忠兵衛、請人伊三郎 宛先 市之瀬村庄屋若五郎殿 役人
奉公人請状
奉公人側が雇主へ提出した身元保証書と労働契約書にあたる。雇主ではなく、雇われる側が労働条件等を書いた。
内容は、奉公の期間、給料の額、お家の作法を遵守しますという誓約、逃亡や長煩いの時の始末、そして江戸時代 はキリスト教禁止のため、すべての人がどこの寺の檀家であるかを明記しなければならなかった。
また、雇われる本人が書くのではなく、身元保証人、大抵は親や親類が書いた。請人(うけにん)は連帯保証人。
◆請人 うけにん
江戸時代の保証人 江戸時代の奉公契約で、雇用者に対し奉公人の人柄や労働能力などを保証する人。
預り申銀子之事. -- (播磨國美嚢郡市之瀬村文書 ; 金融).
21121302/ 所在:貴重 / 請求記号:210.088||119
文化十一年七月
預り手形
これは借金の借用書で、たいてい「預り申銀(金)子之事(あずかりもうすぎん(きん)すのこと」という見出しを使う。「借りる」と書かずに「預かる」と書くところが思いやり。
借りたのは市野瀬村の藤右衛門、貸したのは細枝村の新十郎。銀一貫八百目を借り、月に一分一朱の利息をつけ十二月に返済する旨を記している。
連帯保証人の五人組の連名と印鑑に加え、庄屋の名前・印鑑が見られる。金額・預かったこと・利子・月切りでの言葉の横にも認印を押している。
◆五人組 ごにんぐみ
江戸時代の隣保制度で、百姓・町人の連帯責任、相互監察、相互扶助のために組織させた。
差上申一札. -- (播磨國美嚢郡市之瀬村文書).
21121265/ 所在:貴重 / 請求記号:210.088||119
文化七年八月
上市之瀬村の長七は奉行所にて吟味(取り調べ)される予定だったが、重病になってしまったため行けない。
そこで村役人たちは長七を村で預かり、その間に自殺したり、逃げたり、その他不注意なことがあった場合は、どんな仕打ちでもお受けしますと申し出ている。
庄屋が村の最高責任者、次いで年寄、同段は同様という意味で年寄が二人。
関西では下から順に名前を書き一番偉い人が最後になる。
◆庄屋 しょうや
江戸時代、一村の長。主として関西での呼称。関東では名主(なぬし)という。
乍恐以書附ヲ御届ケ奉願上候. -- (播磨國美嚢郡市之瀬村文書 ; 戸口1).
21121227/ 所在:貴重 / 請求記号:210.088||119
天保七年三月
丈吉の(財産)株を持っている千代蔵が、大坂町奉行に届出をしている。
丈吉が妻と孫を置いて家出をし、手分けして探したが見つからない。
丈吉という男は忠右衛門から借りた銀の返済が滞っていて昨年7月に出入(訴訟)願いがでている。
さらに野瀬村の勘六からも昨年12月に屏風を取り戻したいという出入願いがでている。
そんな丈吉が出奔してしまった!
出入筋と吟味筋 でいりすじ ぎんみすじ
江戸幕府の訴訟手続きで、「出入」は奉行所が原告と被告を呼び出し、対決審問のうえ、判決を下す手続き。主に民事を扱った。一方「吟味」は、被疑者を奉行所や代官所の独自の判断で召喚して審理するもの。今日の刑事裁判にあたる。
◆大坂町奉行
江戸幕府の職名の一つで、市中の治安維持をはじめ裁判など民政全般にわたり、市中の行政・司法を司った
覚〔御倹約御触書写〕. -- (播磨國美嚢郡市之瀬村文書 ; 御用留3).
21121272/ 所在:貴重 / 請求記号:210.088||119
文政2年12月
御触書 おふれがき
「触」とは法令などを広く知らせることで、御触書は江戸時代、幕府や藩主などから一般の人々に公布した文書や法令そのもののこと。
江戸時代、領主や代官は支配下の村々への命令伝達に「廻状」を用いた。各村では庄屋がその内容を「御用留」に書き写した。
◆御用留 ごようどめ
法令や公務書類を、布達されるごとに書き留めたもの。庄屋の交代の際には書類目録とともに引き継がれた。
実弟子証文之事二
2179831/ 所在:貴重 / 請求記号:【五-3-6-16】
文政三年正月
実弟子証文
芸事に弟子入りするときは誓文書を書き、請人が身元を保証した。
これは、初代豊沢広助義太夫の元に三味線の弟子入りした文吉が出している。
「専励精心稽古に励み、旅行をするときは師匠にちゃんと断って、挨拶のお手紙を書きます。弟子をとるときは人柄を選び、師匠のいうことに背いたときは三味線の世界から差し留めしてもかまいません」といっている。
◆豊澤廣助 とよざわひろすけ 初世(1777‐1824 安永6‐文政7)
義太夫節の三味線奏者。豊沢派の祖。大坂生まれ。文化8年に豊沢と改姓し,広助を名乗る。
花園院宸記 / [花園天皇著] ; 宮内庁書陵部編 -- [複製版] -- 思文閣出版, 1992.6-2015.5.
30759527/ 所在:1階W2 / 請求記号:210.42||60||28
花園天皇の延慶3年(1310年)10月から正慶元年/元弘2年(1332年)11月にわたる23年間の日記。
現存する全35巻のほとんどが宸筆(天皇の直筆)で、鎌倉時代後期を研究する上で貴重な史料。
京都の皇室では後嵯峨天皇の後、二つの血筋が皇位をめぐって対立したので、幕府が両統が交代で天皇位につくよう取り決めた。花園天皇は持明院統、後醍醐天皇は大覚寺統。
後醍醐天皇は鎌倉幕府を倒そう密かにと計画していた。
その密談場所で働いていた妻から情報を聞いた土岐頼員は六波羅探題に密告。
九月十九日の朝、六波羅探題は謀反人土岐頼兼と多治見国長を攻め、合戦の末二人は自害した。
その日の日記に事件の顛末が記されている。
この裏書は後日追記されたもの。
御家書札集 : 全 / 上田素鏡書. -- 須原屋四郎兵衛, 寛延3年.
20911041/ 所在:貴重 / 請求記号:816||48
書札礼
近世以前の手紙(書札)は、差出人と受取人の相互の地位や身分によって書き方が決まっており、これに違反したときは礼を欠いたとみなされた。
そのため手紙の例文集、解説書などが多く作られた。
◆御家 おいえ
書道の流派の一つ。江戸時代には朝廷、幕府などの公用文書に用いられた。寺子屋でも書道の手本となり、実用書体として全国に普及した。
当流手形鑑
2180148 / 所在:貴重 / 請求記号: 【九-3】
文政六年
証文類の文例集。
「預り申銀子之事」から「金子為替手形之事」までの証文文例一九通を収録。江戸時代、証文や契約書の文例とした。
正倉院古文書影印集成 / 宮内庁正倉院事務所編 ; 5. -- 八木書店, 1991.
30105027/ 所在:1階A11閉架 / 請求記号:210.35||47||5
正倉院文書
正倉院宝物には1万数千通にも及ぶ文書類が含まれている。
その大部分を占めるのは東大寺の写経所で使われた業務文書で、もともとは中央官庁が廃棄した文書を譲り受けて、その裏紙を再利用している 。これを「紙背文書(しはいもんじょ)」という。
最も古い大宝2年(702年)の戸籍を始めとした行政文書の裏側に、写経生の業務報告書「手実」、休暇願「請暇解」、欠勤届「不参解」 、借金願「借銭解」など、そこに働く人の姿をいきいきと伝えている。
◆解 げ
下級官司から太政官および直属の上司へ奉る文書。「解す」は「解」を提出すること。
享保元文諸国産物帳集成 / 盛永俊太郎, 安田健編 ; 第5巻. -- 科学書院, 1987. -- (諸国産物帳集成).
21086786/ 所在:1階A10閉架 / 請求記号:210.088||108||5
『摂津国尼崎領産物絵図帳』
尼崎藩が幕府の天命を受けて調査し作成した『産物帳』。
「この図江戸へ出し申さず候」とあるので、これは下書きで、この魚の絵は幕府に提出しなかったようだ。
諸国産物帳
八代将軍徳川吉宗は財政再建のため、海外からの物資輸入を抑え国内の資源を開発するため、全国の諸大名・代官に命じて、各領内の作物・動物・植物・鉱物の分布状況を報告させた。
<立て看板>
あなたのまわりの崩し字、変体仮名
ひらがなが一音一字と決められたのは、なんと明治33年になってからです。それまでは変体仮名といって、一音は一つの文字に限りませんでした。
例えば、「あ」は 阿 安 愛 悪
「い」は 以 意 伊 移 異
変体仮名は今でもまだまだ看板などで使われています。きっとみなさんも何度か目にしたことがあると思いますよ。
須磨駅前にあるすし屋。気づいた人も多いでしょう。「にっ多」と書いています。
下村あなごの包装紙です。「阿奈古゛」と書いています。おいしいアナゴ屋さんです。
三宮にいくつか店舗を構えるたこ焼きたちばな。「太古焼」と読みます。
これはおなじみの割り箸。「おてもと」ですね。「御手茂登」と読めました?
小さい頃“あのよろし”と思っていた花札。「あ可よろし」(あかよろし)です。
ちら見パラ見 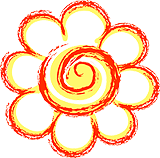
| 資料番号 |
書誌情報 |
請求記号 |
元の所在名称 |
| 30866041 |
古典籍古文書料紙事典 : 必携 / 宍倉佐敏編著. -- 八木書店, 2011.7. -- viii, 453, ixp : 挿図 ; 22cm. |
022.6||Sh |
3階R3 |
| 30355569 |
古文書の補修と取り扱い / 中藤靖之著. -- 雄山閣出版, 1998. -- 221p, 図版2枚 ; 21cm. |
022.8||3 |
3階R3 |
| 72002612 |
須磨寺「當山歴代」 : 摂津国八部郡福祥寺古記録 / 三浦真厳編纂 ; [平装]. -- 須磨寺塔頭正覚院, 1989.3. -- 301p, 図版 [12] p : 挿図 ; 30-31cm. |
188.55||1C |
1階A8閉架 |
| 20421847 |
古文書鑑 : 様式と筆蹟 / 村田正志編. -- 続群書類従完成会, 1980. -- 56,18p ; 19×26cm. |
210.02||41 |
3階N13 |
| 30728233 |
古文書はこんなに魅力的 / 油井宏子著. -- 柏書房, 2006.2. -- 288p : 挿図 ; 21cm. |
210.02||Ab |
3階N13 |
| 30728196 |
古文書入門 : 判読から解読へ / 藤本篤著. -- 柏書房, 1994.9. -- 164p ; 21cm. |
210.02||Fu |
3階N13 |
| 30730410 |
古文書検定 / 油井宏子監修 ; 柏書房編集部編 ; 入門編. -- 柏書房, 2005.10. -- 156p ; 21cm. |
210.02||Ka |
3階N13 |
| 30506381 |
古文書学入門 / 佐藤進一著. -- 新版. -- 法政大学出版局, 1997.4. -- xiii, 316, 18p, 図版40p ; 21cm. |
210.02||Sa |
3階N13 |
| 21521706 |
百人の書蹟 : 古文書入門 / 永島福太郎著. -- 淡交社, 1965. -- 231p 図共 ; 22cm. |
210.029||1 |
移動書架B17閉架 |
| 21959387 |
近世の村・家・人 / 国文学研究資料館史料館編. -- 名著出版, 1997.3. -- 400p, 図版1枚 ; 22cm. -- (史料叢書 / 国文学研究資料館史料館編 ; 1). |
210.088||156B||1 |
1階A10閉架 |
| 21948305 |
東大寺文書の世界 : 国宝指定記念 : 特別展 / 奈良国立博物館編集. -- 仏教美術協会, 1999.2. -- 178p : 挿図 ; 30cm. |
210.088||Na |
2階図録等 |
| 22051530 |
中世の古文書 : 機能と形 : 企画展示 / 国立歴史民俗博物館編集. -- 国立歴史民俗博物館, 2013.10. -- 221p : 挿図 ; 30cm. |
210.4||Ko |
2階図録等 |
| 30881624 |
戦国大名の古文書 / 山本博文, 堀新, 曽根勇二編 ; 東日本編. -- 柏書房, 2013.8-2013.12. -- 2冊 ; 22×31cm. |
210.47||Ya |
3階N16 |
| 30890688 |
戦国大名の古文書 / 山本博文, 堀新, 曽根勇二編 ; 西日本編. -- 柏書房, 2013.8-2013.12. -- 2冊 ; 22×31cm. |
210.47||Ya |
3階N16 |
| 21515439 |
古文書が語る近世村人の一生 / 森安彦著. -- 平凡社, 1994.8. -- 175p ; 19cm. -- (セミナ-「原典を読む」 ; 4). |
210.5||145 |
移動書架B17閉架 |
| 30767003 |
書翰初学抄 : 江戸時代の手紙を読むために / 田中善信著. -- 改訂. -- 貴重本刊行会, 2004.7. -- 174p ; 21cm. |
210.5||Ta |
3階N16 |
| 21418891 |
女用訓蒙図彙 / 奥田松柏軒著 ; 田中ちた子,田中初夫編ならびに解説. -- 渡辺書店, 1970. -- 295p ; 25cm. |
384.6||9 |
移動書架B4閉架 |
| 30023550 |
国宝 / 長峰八州男編 ; 11. -- 毎日新聞社, 1989. |
709.1||43||11 |
3階M2 |
| 30092228 |
新指定重要文化財 / 「重要文化財」編纂委員会編 ; 解説版 9. -- 毎日新聞社, 1984. -- 261,11p ; 27cm. |
709.1||44||9 |
1階C1閉架 |
| 30741928 |
くずし字解読辞典 / 児玉幸多編 ; : 新装. -- 東京堂出版, 1993.2. -- 336, 61p ; 19cm. |
728.4||Ko |
3階L |
| 70086256 |
くずし字用例辞典 / 児玉幸多編 ; 新装版. -- 東京堂出版社, 1993.6. -- 8,1305,63p ; 22cm. |
728.4||Ko |
事務室・カウンター |
|